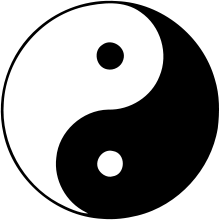 武術太極拳とは
武術太極拳とは
日本では太極拳が広くおこなわれるようになって、約40年がたちます。
近年では長拳、南拳や各種の伝統武術が若い世代を中心に親しまれています。
中国武術は国際的には「武術」の中国語の発音であるWUSHU(ウーシュー)の名称で普及しています。
太極拳は武術(WUSHU)の中の一種目ですが、日本では太極拳の愛好者人口が圧倒的に多いことから、
太極拳と各種の中国武術・中国拳法を総称して、「武術太極拳」の名称で普及を進めています。
日本での愛好者はすでに100数十万人となり、その普及・発展は顕著なものがあります。
うち女性は約7割、男性は3割位で、若い人の関心も近年高まっています。
競技人口は70,000人(ジュニア年代約1万人)と言われています。
2020年12月17日にはユネスコの世界無形文化遺産のリストに「太極拳」として登録されています。
日本でも国体公開競技として認められ2019年茨木国体から参加しています。
中国武術の起源は数千年前に遡りますが、14世紀から20世紀始めにかけて特に目覚しく発達して、
打つ、蹴る、投げる、つかむ,刺す等の技法を組み合わせた数多くの武術の流派、種類が生まれました。
現在行われている武術は200~300種類あると言われ、力強く速い動作を主体にしたものから柔らかく、巧妙な技を使うものまで
多岐にわたります。
格闘技としての武術は、社会状況の変化につれて、しだいに健身、スポーツ種目として心身の鍛錬と修養を
目的とするようになりました。
合理的でかつ、高度な技術体系を有する運動であり、これをおこなうことに芸術表現の喜びを得ることもできるため、
近年、日本、アジア諸国や欧米各国でも広範な社会層の愛好者人口を得るにいたっています。
日本では太極拳技能検定制度が1995年から全国的に導入・実施され、愛好者に目的を与え向上心を促すものとして歓迎され、
太極拳の普及振興を進めるうえで大きな役割を果たしています。